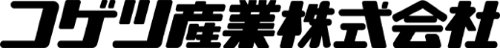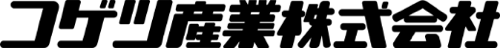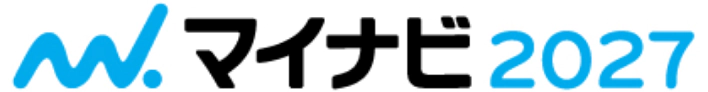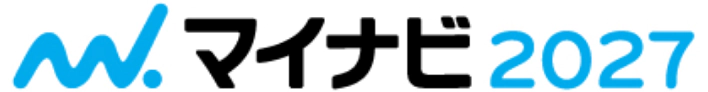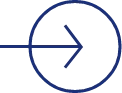発注ボタンを押すだけじゃない――仕入れの世界は、思っているよりずっとクリエイティブだ。
「卸売って、倉庫と得意先をただ行ったり来たりするだけじゃないの?」
「専門的なスキルやマーケティングなんて縁がなさそう。」
そんなイメージを持っている人ほど、コゲツ産業で働く人たちの仕事のリアルを知ったら、驚くはずです。
食品卸の現場で日々行われているのは、まさに“情報と感覚の勝負”。
世の中の変化に敏感にアンテナを張り、“次に来るもの”を読み取り、タイミングよく仕入れる。そこには、単なる作業ではなく、マーケティングやトレンド分析の要素すら含まれているのです。
たとえば、毎年のようにトレンドが変わるクリスマス商材やおせちの世界。
テレビや雑誌、SNS、さらには、スーパーの棚の様子まで、あらゆる情報がヒントになります。
「今年は○○スイーツが来るらしい」と聞けば、そこから新しい提案を生み出せるのが、この仕事の面白さ。
つまり、仕入れとは“商品を選ぶ”ことではなく、“売れる未来をつくる”こと。
そしてそれは、世の中の空気をいち早く察知し、行動につなげられるかどうかにかかっています。
「なんとなく最近この味多くない?」「このキーワード、よく聞くな」
そんな日常の中の小さな気づきが、大きな提案につながる。
仕入れはまさに、日常を武器にできる仕事です。

信頼がすべて。仕入れ判断は“届ける責任”とセットで考える
どんなに話題の商品でも、どれだけ魅力的な提案でも――
それが確実に欲しいタイミングで届かなければ、すべてが水の泡になる。
食品業界では、商品そのものの良さだけでなく、それをきちんと届けられるかどうかが信頼を分ける分岐点です。
特に鮮度が命の商材では、わずか数時間の遅れが、売り場の穴や販売機会の喪失、最悪の場合は廃棄ロスにつながることも。
たった一つの仕入れ判断ミスが、得意先との信頼関係をガラガラと崩してしまう世界なのです。
ここで問われるのが、読みの先にある“段取り力”。
どこから仕入れ、どのルートを通し、いつ届けるか――。
たとえば、九州のメーカーから山口のスーパーに商品を届ける際にも、渋滞情報や天候、センターの混み具合など、あらゆる要素を加味した上で最適解を導き出す必要があります。
しかも、仕入れ担当はただの中継者ではありません。
発注内容を考え、納品日を調整し、在庫の波を読んで先回りする――
そんな、“最前線の司令塔”のような役割を担っています。
店舗の棚に商品が並ばなければ、消費者は「このお店、品揃え悪いな」と感じます。
その評価は、お店だけでなく、流通を担う卸業者にも跳ね返ってきます。
だからこそ、裏側を知り尽くした仕入れ担当が完璧な段取りを組み、信頼を積み重ねていく必要があるのです。
実際、コゲツ産業の現場では、『物流の仕組みまで理解してこそ、本当の仕入れができる』という考えが根付いています。
取引先に対して、「この商品はこのタイミングであれば、最短で納品できますよ」と一歩先の提案ができるかどうか。
仕入れの仕事には、価格や品質の判断だけでなく、納品までの流れを設計する力が求められるのです。
こうした緻密な判断が、得意先からの「コゲツ産業に任せていれば安心」という信頼をつくっていく。
仕入れは、ただ商品を選ぶだけの仕事ではありません。
それは、“信頼“という無形の価値を、商品に乗せて届ける仕事でもあるのです。
座学だけでは終わらない。実務の中で、“使える力”が身につく
どんな判断も、いきなりできるようになるわけではありません。
だからこそコゲツ産業では、まず現場を知ることからすべてが始まります。
入社1年目は、営業に出る前の大切な土台づくりの時間。物流の流れ、商品が届くまでの過程、仕入れの前後にあるリアルな現場――それらを実際に体験し、理解することで、自分の提案や判断に“深み”が生まれてくるのです。
研修では、センターでの仕分けや在庫管理、伝票処理など、現場の業務を体験します。
「この伝票1枚の間違いが、納品ミスに直結してしまう」
「商品が届くタイミングを一日間違えると、こんなに影響が出るんだ」
そうしたリアルな気づきが、机の上では学べない感覚として身についていきます。
そして2年目からは、いよいよ得意先を持ち、営業として現場に出ていきます。
最初はもちろん、先輩のサポートのもとで進めていくことになりますが、ただ「やってみて」と任せられるのではなく、「こういう判断をすると、こうなるよ」と背景まで丁寧に教えてもらえる。
その積み重ねが、「なぜその提案をするのか?」「どこに注意が必要なのか?」という思考の軸を自分の中に持たせてくれるのです。
成長とは、教えられて身につけるものではなく、試してみる中で育つもの。
コゲツ産業には、そうした挑戦を当たり前にできる環境があります。
現場を知っているからこそ、提案が深まる。流れを体験しているからこそ、判断に説得力が生まれる。
コゲツ産業では、“感覚”を“力”に変えるステップが、しっかり用意されているのです。
判断力の先にある、“経営感覚”という武器
若手だからといって、目の前の数字だけを追って終わり――ではありません。
コゲツ産業では、現場での判断を重ねるなかで、自然と経営感覚が鍛えられていく環境があります。
単なる営業・仕入れの枠を超えて、「どうすればこの取引先にとって最適か」「どうすれば会社全体の利益が最大化できるか」を考える機会が、日常の中に溢れているのです。
たとえば、福岡に配属された若手社員は、大分・熊本・長崎・宮崎といった広域を担当。
配送ルートや物流センターの位置を意識しながら、どの商品をどこに、どのタイミングで、どのルートで届けるかを逆算し、提案や仕入れを行っています。
その判断ひとつで、配送効率も、得意先の信頼も、最終的な利益さえも大きく変わってしまう。だからこそ、単に売るという行為の先にある“利益を設計する思考”が求められるのです。
こうした視点は、入社直後からすぐに身につくわけではありません。
けれど、日々の業務の中で「この判断、どうしてこうしたんだろう?」「もっと効率の良いルートってないかな?」と自問自答を繰り返していく中で、少しずつ育っていきます。
その成長の手応えを感じられるのが、現場で判断する面白さであり、卸売のプロとしてのやりがいでもあるのです。
さらに、全国規模の広域にわたる得意先を担当した場合。
決して甘くはありませんが、その分、成長できる環境があるのも事実。
『提案ひとつで商談が前に進む』『物流調整でコストが改善される』――
そんな成功体験を重ねていくうちに、次第に自分の判断が誰かの仕事を支えているという実感が湧いてくるのです。
上司や先輩は、単に答えを与えるのではなく、自分で考えられるようになることを後押ししてくれます。
だからこそ、「自分の考えを形にしたい」「現場を動かす立場になりたい」と思ったとき、若手でも挑戦できる余地がある。
年齢や社歴に関係なく、“視野を広げたい”という意欲がある人ほど、大きく成長していける会社なのです。
現場の感覚を持ちつつ、全体の流れを読む――。
コゲツ産業の若手は、そんな“地に足のついた経営視点”を、実務の中で育てていきます。

売るより考えることが好きなあなたへ――仕入れは未来を動かす仕事。
商品を提案し、仕入れ、確実に届ける――
一見シンプルに見えるこの流れの中に、いくつもの考えるポイントが詰まっています。
「今どの商品が売れるか? 」「どこに、どのルートで、どう届けるべきか?」
仕入れという仕事は、目の前の“モノ”を扱っているようでいて、実は“未来”を扱っている仕事です。
市場の動向、得意先のニーズ、物流の制約、天候や季節感――
あらゆる要素を組み合わせ、「これが最適だ」と判断を下す。
そして、その決断の先に、スーパーの棚が動き、お客様の食卓が変わる。
仕入れの仕事は、現場を支える仕事であると同時に、社会と暮らしを動かす仕事でもあるのです。
しかも、それを担うのに、特別な資格や完璧な経験は必要ありません。
必要なのは、日常の中で「なぜ?」「どうして?」と考える力と、
「もっと良くしたい」「相手に喜んでもらいたい」という感性。
流行に敏感な人、身の回りの変化にすぐ気づく人、何かを深掘りして考えるのが好きな人――
そんな人ほど、仕入れの世界では輝けます。
もちろん、最初からうまくいくことばかりではありません。
読みが外れることもあるし、段取りの甘さで失敗することもある。
でもコゲツ産業には、その失敗を学びに変える風土があります。
一人で抱え込むのではなく、先輩たちが一緒になって答えを探してくれる環境がある。
だからこそ、安心して挑戦できるし、失敗から成長できるのです。
“売る”よりも、“考える”ことが好き。
“作業”よりも、“仕組み”に興味がある。
そんなあなたには、仕入れの仕事が驚くほどフィットするかもしれません。
次のヒット商品を選ぶのは、あなたの“読み”かもしれない。
次の季節の売り場をつくるのは、あなたの“決断”かもしれない。
仕入れという仕事には、そんな未来を動かす力があります。